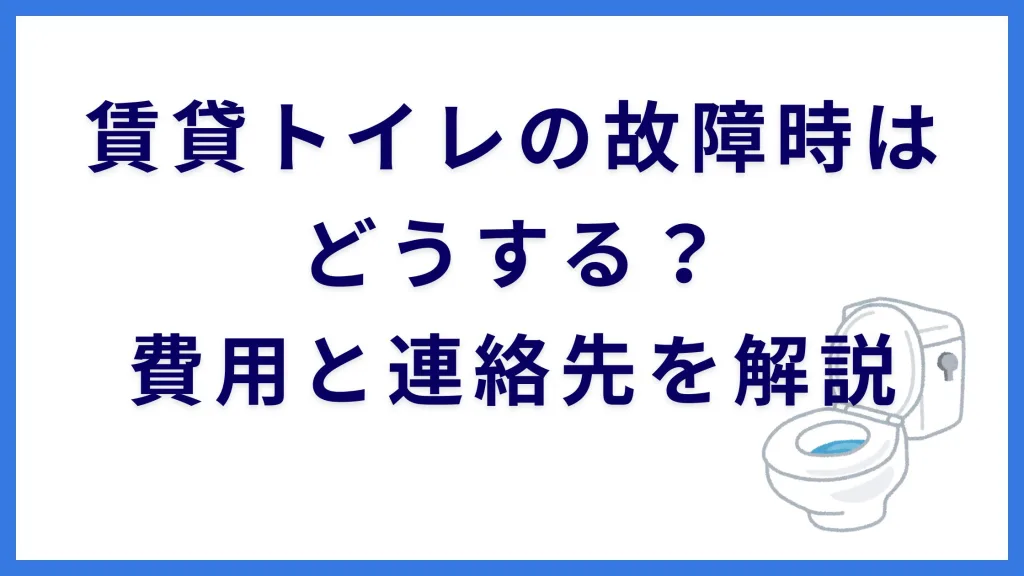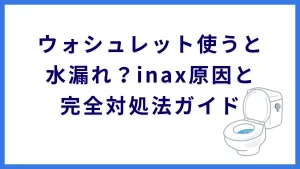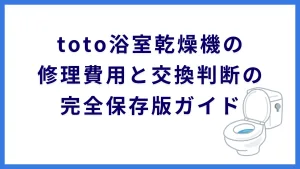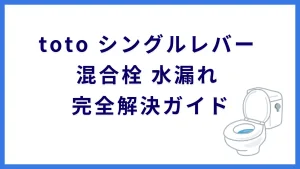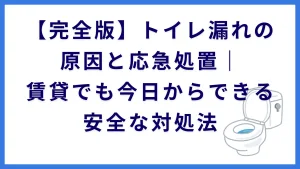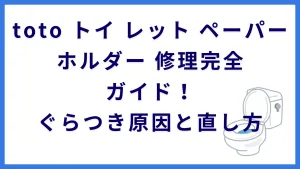一人暮らしの賃貸に住んでいる方なら、
「夜中にトイレが壊れてしまって、誰に連絡すればいいのか分からない…」
「これって自分で修理業者を呼んでいいの?それとも管理会社?」
「修理代って、まさか全部自腹になるの?」
このような不安や疑問を抱えているかもしれませんね。
賃貸住宅でトイレが故障した場合は、まず契約書の確認、次に管理会社への連絡、そして応急処置という3ステップで落ち着いて対応するのが基本です。
この3つの手順を知っていれば、深夜や休日に突然トラブルが起きたとしても慌てず、適切に判断しながら最短ルートで解決に向かえます。
結果的に、不要な出費や被害の拡大を防ぐことにもつながりますよ。
この記事では、賃貸物件でのトイレトラブルに悩む方に向けて、
– 契約書のどこを確認すればよいか
– 管理会社や大家に正しく伝えるべき情報
– 応急処置の具体的なやり方と注意点
– 修理費用が誰の負担になるかの判断基準
– 管理会社と連絡が取れないときの対処法
上記について、水まわり修理の専門家としての視点を交えながら解説しています。
突然のトラブルにも冷静に対応できるように、ぜひ参考にして今後の備えとしてお役立てください。
Contents
賃貸のトイレが壊れた!焦らず確認すべき3つの基本対応
突然トイレが使えなくなったとき、多くの人は「どうしよう」とパニックに陥るかもしれません。
ですが、賃貸物件でのトイレ故障は、3つのステップで冷静に対応することが可能です。
そのステップとは「契約書の確認」「管理会社または大家への連絡」「応急処置」。
この流れに沿って対応すれば、修理費の負担者や今すぐ取るべき行動が明確になり、無駄な出費や被害拡大を防げます。
まずは、現在の状況が「貸主負担」「入居者負担」どちらに該当するかを判断することが大切です。
その手がかりになるのが、賃貸契約書に書かれた修理・設備に関する条項。
それでは、ひとつずつ具体的に確認していきましょう。
まずは契約書の「修理・設備」欄をチェック
トイレが故障したとき、最初に確認すべきなのは「賃貸契約書」です。
ここには、修理の範囲や責任の所在が明確に記載されていることがほとんど。
多くの場合、「貸主が修理・交換を行う設備」「入居者が日常的に管理・掃除する範囲」といった記載があります。
例えば、トイレ本体の故障や水漏れなどは「貸主負担」とされるケースが一般的です。
一方で、異物を流して詰まったなど、明らかに入居者の過失が原因のトラブルは「入居者負担」となる可能性があります。
「自分のせいではないと思うけれど、本当にそうなのか不安…」という方は、契約書のコピーを手元に置いておくと安心です。
不明な場合は、次のステップで管理会社に確認しましょう。
管理会社または大家への連絡は何を伝える?
契約書で責任の所在をある程度確認したら、すぐに管理会社または大家さんに連絡を入れましょう。
このとき、以下の情報を明確に伝えるとスムーズです。
– **故障の症状**:例)「水が流れない」「ずっと水が出続けている」
– **発生した日時**:いつから発生しているのか
– **自分で試した対処法**:止水栓を閉めた、ラバーカップで試した等
– **被害の状況**:水漏れによる床への影響など
「深夜だけど、連絡していいのかな…」と迷う方もいるかもしれません。
ですが、夜間用の緊急連絡先を設けている管理会社も多く、まずは電話してみる価値はあります。
万一つながらない場合に備えて、留守番電話に要点だけでも残しておくと、翌朝の対応が早まることもあります。
夜間や休日の応急処置:止水栓で水漏れを防ぐ方法
連絡がつかない、業者が来るまでに時間がかかる——そんなときは、応急処置が重要です。
最も基本的かつ効果的なのが、「止水栓(しすいせん)」を閉めて水を止めること。
止水栓は、トイレタンクの近く、または床にある銀色のバルブで、手で回すかマイナスドライバーで操作します。
以下の手順で止水処置を行ってください。
1. タンクや便器の下部にある止水栓の位置を確認
2. 時計回りにゆっくりと回し、水の供給を止める
3. 水が止まったことを確認し、床にタオルなどを敷いておく
「これで水漏れはひとまず止められた…」という安心感が、不安な夜を乗り切る助けになります。
ただし、タンク内の部品や配管など、無理にいじるのはおすすめしません。
応急処置はあくまで被害の拡大防止が目的。
翌朝、管理会社や専門業者に状況を詳しく説明し、正式な修理依頼をしましょう。
修理費は誰が払う?賃貸物件での費用負担ルールを解説
トイレの故障が発生すると、まず気になるのが「修理費は誰が払うのか?」という点ではないでしょうか。
この疑問に対する答えは、「故障の原因が何か」によって異なります。
設備の老朽化による自然故障なら原則として大家(貸主)の負担になる一方で、使用者側の不注意によるトラブルであれば、入居者が修理費を負担する可能性もあります。
ここでは、判断のポイントや事例を交えながら、費用負担のルールを分かりやすく整理していきます。
設備の経年劣化なら「大家負担」が原則
結論から言えば、経年劣化や通常使用における自然故障は、大家側の責任で修理されるのが一般的です。
賃貸借契約における「貸主の修繕義務」によって、設備の維持管理は基本的に貸主側の責任とされています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
例えば以下のようなケースでは、大家負担になることが多いです。
– **タンク内部の部品の劣化**:
長年の使用によってゴムフロートやボールタップなどが劣化し、水が止まらない場合。
– **配管の腐食や破損**:
配管自体の経年劣化が原因で漏水した場合。
– **便器や便座の破損(自然損耗)**:
使用頻度に応じて自然に起こった破損で、入居者の過失がないと判断されるもの。
これらは「入居者の通常使用による消耗」とされ、原則として修理費を請求されることはありません。
ただし、契約書に「軽微な修繕は入居者負担」などの特約がある場合は、その範囲に含まれるかどうかを確認しましょう。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
自分の過失や使い方による故障は「入居者負担」に
一方、入居者の過失によるトラブルは、修理費を請求される可能性があります。
「過失」とは、注意を怠ったり、通常では考えにくい使い方をしてトラブルを招いた場合を指します。
たとえば、以下のようなケースです。
– **異物の投入による詰まり**:
生理用品やおむつなど、本来トイレに流してはいけないものを流してしまった場合。
– **清掃時のミスによる破損**:
便器に強い衝撃を与えてヒビが入ったり、薬品で部品を劣化させた場合。
– **子どものいたずらや故意の破損**:
玩具を流したり、タンクの蓋に乗って割れたなど、明らかな使用ミスがあった場合。
「まさかこんなことで…」ということが修理費の請求対象になることもあります。
「うちは大丈夫だろう」と油断せず、日頃から使用方法に注意することがトラブル予防にもつながります。
判断に迷ったら?管理会社に確認するべきポイント
トイレの故障が起きたとき、「これは自分の責任なのか?」「管理会社に任せていいのか?」と判断に迷うこともあります。
そんなときは、管理会社へ状況を正確に伝え、判断を仰ぐのが最も確実です。
以下の情報を事前に整理しておくと、連絡がスムーズになります。
– **故障の症状**(例:水が止まらない、流れない、変な音がするなど)
– **発生した日時**(いつから起きているか)
– **自分で試した対応**(止水栓を閉めた、異物がないか確認した等)
– **過去にも同じトラブルがあったかどうか**
管理会社側でも、状況を聞いた上で「専門業者を手配するか」「入居者で対応可能か」などの判断をしてくれます。
また、修理費の負担についてもこの時点で確認しておくと、後々のトラブルを回避できます。
「これって自腹?」と悩む前に、まずは冷静に状況を整理して相談することが、最短での解決につながります。
よくあるトイレ故障の原因とその見分け方
賃貸物件のトイレに不具合が起きたとき、まず大切なのは「原因の特定」です。
故障の種類によって連絡先や修理の優先度、費用の負担範囲が大きく変わってくるからです。
特に賃貸では、自分で業者を呼ぶ前に「これは自然故障?それとも使用ミス?」を見極める必要があります。
ここでは、水が流れない・止まらない・詰まるといった「よくあるトイレの故障」について、それぞれの見分け方を解説します。
レバーを押しても流れない場合の原因とは?
「何度レバーを押しても水が流れない…」というトラブルの原因は、大きく2つに分かれます。
1つ目は、タンク内の部品の不具合です。
2つ目は、止水栓が閉まっていてそもそも水がタンクに入っていないケースです。
前者の場合、以下の部品が故障している可能性があります。
– **チェーンの外れ**:
レバーの操作とタンク内の弁をつなぐチェーンが外れると、水が流れません。
[参照URL: https://uchi.tokyo-gas.co.jp/restroom/0042]
– **フロートバルブの不具合**:
フロートバルブが正しい位置にはまっていないと、水が流れない原因となります。
[参照URL: https://jsgt.jp/column/toilet/water-notflow/]
– **レバー本体の破損やゆがみ、サビ**:
レバー自体が破損していたり、サビついていたりすると、正常に作動しません。
[参照URL: https://jsgt.jp/column/toilet/water-notflow/]
また、止水栓(トイレ本体の下部についている水の元栓)が何らかの理由で閉じていると、タンクに水が供給されません。
「水がそもそもたまっていない」場合は、止水栓が動作しているかどうかをまずチェックしましょう。
「レバーは動くけど水が出ない…」というときは、タンクの中をそっと開けて確認するのが第一歩です。
水が止まらない・漏れるときはどこを見ればいい?
「水がいつまでも流れて止まらない」「便器の下が濡れている」という症状もよくあるトラブルのひとつです。
この場合、まずチェックすべきはタンク内部と配管接続部です。
主な原因には以下のようなものがあります。
– **ゴムフロートの劣化による水漏れ**:
ゴムフロートが劣化すると、排水口をしっかりとふさぐことができず、水が流れ続けてしまいます。
[参照URL: https://0120245990.com/column/wc/rubber-float-trouble.html]
– **ボールタップの故障**:
ボールタップが故障すると、水位を適切に感知できず、水が止まらなくなることがあります。
[参照URL: https://gifu-suido-pro.com/column/16080/]
– **給水管やパッキンからの漏れ**:
タンクと壁・床をつなぐ給水管のナットが緩んでいたり、内部パッキンが劣化している場合も水漏れの原因になります。
[参照URL: https://www.qracian.co.jp/column/toilet/12120/]
床が濡れていたら「便器からの逆流?」と焦るかもしれませんが、実はタンクや配管からの水滴だった、というケースも多いです。
タオルで拭き取りながら、どの箇所から水が出ているのかを慎重に観察してみてください。
詰まりや逆流は異物混入が原因?確認の仕方と注意点
トイレの詰まりや逆流トラブルの多くは、「流してはいけないものを流してしまった」ことが原因です。
とくに以下のような異物は、排水管内での詰まりを引き起こしやすいです。
– 生理用品
– ティッシュペーパー(トイレットペーパーではない)
– おむつ・猫砂・掃除用シート
– プラスチック製のおもちゃなど
「紙類だから流しても平気かな」と思っても、トイレットペーパー以外は基本NGです。
異物が原因かどうかを見極めるには、まず水位の変化をチェックしましょう。
水を流したあとに便器内の水が上がってきたり、逆流するようであれば、詰まりの疑いが高いです。
また、ポコポコと空気の音がする場合も、排水管内に空気や水がうまく流れていない証拠です。
軽度の詰まりであれば、ラバーカップ(スッポン)で解消することも可能ですが、無理に押し込むと逆に悪化することもあるため注意が必要です。
「何か落としたかも」「触るのが怖い…」というときは、無理せず管理会社や業者に連絡するのが安全です。
緊急時の応急処置でパニック回避!自分でできる対処法
トイレの故障は、突然やってきます。
特に夜間や休日に限って「水が止まらない」「逆流した」「レバーが効かない」などのトラブルが発生すると、誰でも焦ってしまうものです。
ですが、そうしたときこそ大切なのは“冷静さ”。
このセクションでは、自分でできる応急処置の方法を、実際の現場目線から分かりやすくお伝えします。
あくまで「専門業者が来るまでのつなぎ」としての対応ですが、知っておくことで被害の拡大を防げるケースは少なくありません。
水を止める止水栓の位置と回し方
トイレの水が止まらないとき、まず最優先でやるべきは「止水栓を閉める」ことです。
止水栓は、トイレ本体に水を供給しているバルブで、これを締めれば水の供給を一時的にストップできます。
焦ってしまいがちですが、「止水栓ってどこ?どうやって閉めるの?」という状態で手が止まる方も多いはずです。
以下に、止水栓の基本情報をまとめました。
– 位置の目安:
便器の左側または右側の壁際、床付近に設置されていることが多いです。銀色の配管の途中にある、マイナスドライバーで回すネジのようなパーツがそれです。
[参照URL: https://jp.toto.com/support/repair/toilet/howtoclose_adjust_waterstopcock]
– 回し方のコツ:
マイナスドライバーがあれば「時計回り(右回り)」に数回回すと、水が止まります。ドライバーがなければ、硬貨や平たいスプーンの柄などで代用可能です。
[参照URL: https://www.lixil-reform.net/useful/waterrelated/toilet/09/]
– 完全に閉じる必要はない:
無理に締めすぎると破損の原因になるので、水が止まった時点で一旦ストップしましょう。
[参照URL: https://uchi.tokyo-gas.co.jp/restroom/0041]
「止まらない水を見てパニックになりそう…」というときは、まず深呼吸。
そのうえで、止水栓を探して水を止める。
この一手で、被害を最小限に抑えられます。
タンク・便器まわりを傷つけずに対処するコツ
応急処置をする際、意外と多いのが「部品を外そうとして壊してしまった」というケースです。
とくにタンクの中は、見慣れない部品が多いため、やみくもに手を出すのは避けたいところ。
以下の点に注意しながら、慎重に対応しましょう。
– タンクのフタは両手で水平に持ち上げる:
一部のタンクは陶器製で重く、滑りやすいため、無理に片手で扱うと割れることがあります。
[参照URL: https://jp.toto.com/support/repair/toilet/howtoclose_adjust_waterstopcock]
– 内部に触れるときはゴム手袋を:
水が汚れている場合や、感電防止のためにも手袋の使用をおすすめします。
[参照URL: https://www.lixil-reform.net/useful/waterrelated/toilet/09/]
– 異音や臭いが強いときは無理に触らない:
異物混入や下水トラブルの可能性もあるため、触らず専門業者を待ちましょう。
– ラバーカップを使う場合の注意:
詰まりを除去する際、ラバーカップ(スッポン)は便器の水が溜まっている部分にしっかり密着させ、ゆっくり押してから一気に引き抜く動作が基本です。
「急いで解決したい」と焦る気持ちは自然ですが、勢いだけで行動すると余計な破損を招きかねません。
目の前のトラブルに冷静に向き合うことが、最も早い解決への近道です。
「これは自分で対応してはいけない」ケースもある!
一見すると「ちょっとした不具合」に思えても、実は自分で対応すると危険なケースも存在します。
次のような状況では、無理に応急処置を行わず、すぐに専門業者か管理会社に相談しましょう。
– 水が逆流してあふれそうなとき:
便器から汚水が上がってきている場合は、配管の深部で詰まりが起きている可能性があります。自力対応はリスクが高く、床や壁への二次被害も起こりやすいため、止水栓を閉めて対応を待ちましょう。
– 異臭が強くする場合:
下水の臭いが強く漂っている場合、排水管や排気管のトラブルが疑われます。これは居住者では対応できない範囲です。
– 電気部品が濡れている・漏電の恐れがある場合:
温水洗浄便座など電気を使用する設備が濡れていると感電の危険があります。絶対に触らずブレーカーを落としてから連絡を。
こうしたケースは、「自分がなんとかしなきゃ…」と思うほど判断を誤りがちです。
でも本当に大切なのは、「無理をしない」こと。
自分でできることと、そうでないことを見極める判断力が、賃貸での生活では何よりのスキルです。
管理会社と連絡がつかないときの選択肢
トイレの故障が発生したのに、管理会社と連絡がつかない――そんなとき、どう対応すべきか悩む方は少なくありません。
特に夜間や休日、あるいは担当者が不在のケースでは「誰に頼ればいいのか」「勝手に業者を呼んで大丈夫?」と判断に迷ってしまうものです。
このセクションでは、連絡手段が見つからないときの探し方から、相談先、そして自分で業者を手配する場合の注意点までを具体的に解説していきます。
連絡先が分からないときに探すべき場所
「契約時にもらった資料が見当たらない」「管理会社の名前は覚えているけれど、連絡先が分からない」といった状況は意外とよくあります。
そんなときは、以下の方法で情報を探してみてください。
– **賃貸契約書類を再確認する**:
契約書の表紙または末尾に、管理会社や大家の連絡先が記載されていることが多いです。ファイルの中や封筒に紛れている場合もあるので、見落としがないよう確認しましょう。
– **室内の目立つ場所をチェック**:
インターホンの近く、玄関付近、キッチンの壁などに、管理会社のステッカーやマグネットが貼られていることがあります。
– **ポストや集合ポスト周辺を確認**:
マンションやアパートでは、掲示板に管理会社の緊急連絡先が貼ってあるケースもあります。
– **不動産会社へ直接問い合わせる**:
契約時に仲介した不動産会社がわかる場合は、そこに連絡して確認することも可能です。
「どこにも書いていない…」と感じても、焦らず周囲の情報を探ってみましょう。
思わぬ場所にヒントが隠れていることがあります。
対応が遅い・音信不通…そんなときの相談先は?
管理会社に連絡がついたとしても、「対応は明日になります」「設備担当が休みで…」と言われてしまうこともあるでしょう。
そうした場合、以下のような“セカンドライン”の相談先を検討するのがおすすめです。
– **管理会社のコールセンターや提携サービス**:
大手管理会社であれば、夜間や休日専用のコールセンターや提携の水道修理サービスが用意されている場合があります。緊急対応窓口の有無を確認しましょう。
– **火災保険の付帯サービス**:
賃貸契約時に加入する火災保険には、実は「水まわりの応急対応」などの無料サービスが付いていることがあります。保険証券を確認し、コールセンターに問い合わせてみてください。
– **地域の水道局・市区町村の相談窓口**:
公的な水道局では、上下水道の緊急トラブルについて相談できる場合もあります。修理までは対応しませんが、アドバイスを受けられることがあります。
– **民間の消費者相談窓口**:
「対応が遅すぎる」「修理費を請求されたが納得できない」といったトラブルは、消費者センター(消費生活センター)に相談可能です。
「今すぐどうにかしないと困る…」という気持ちになるかもしれませんが、こうした相談先を知っておくことで、少し冷静になれるかもしれません。
自分で業者に依頼する場合の注意点と費用相場
どうしても連絡が取れない、または水漏れなどで緊急性が高い場合、自分で業者に依頼する判断も必要になることがあります。
ただし、業者手配には注意点があるため、以下をよく確認してください。
– **管理会社への事後報告は必須**:
自分で修理を依頼する前に、「応急処置として修理を行ったこと」「どこの業者に依頼したか」「費用はいくらかかったか」などを記録し、後日すぐに報告しましょう。
– **修理費用は一時的に自己負担となる可能性がある**:
経年劣化などによる故障であれば、原則として大家側の負担となりますが、事前確認なしの業者依頼だと立替が必要になるケースもあります。
– **業者選びは慎重に**:
「24時間対応」「即日修理OK」とうたう業者でも、高額請求や不要な作業をされるリスクもゼロではありません。実績があり、料金表が明確に提示されている業者を選ぶのが安心です。
– **費用相場を事前に調べておく**:
トイレの詰まり除去や簡易な修理であれば、5,000~15,000円程度が相場です。深夜料金や緊急対応料が加算されることもあるため、依頼前に必ず見積もりを確認しましょう。
筆者の経験から言えば、「まず止水栓を締めて水を止めておき、翌朝管理会社に連絡してから対応する」というのが、最も無難なケースが多いです。
とはいえ、状況によっては「今すぐにでも処置しないと床が水浸しになる」ということもあります。
その判断が必要になったときのために、こうした情報を頭の片隅に入れておくと安心です。
【FAQ】賃貸トイレ故障でよくある質問とその答え
トイレの故障は突然起こるため、混乱や不安がつきものです。
特に賃貸物件では「誰に連絡すればいいの?」「費用は自分持ち?」といった疑問が次々と湧いてくるはず。
ここでは、実際に現場でよくいただく質問とその答えをQ&A形式で解説します。
「これってどうなるの?」と悩んでいる方のモヤモヤが、少しでも晴れるヒントになればと思います。
修理費をあとから請求された…支払い義務はある?
原則として、設備の自然故障や経年劣化による修理は貸主(大家さん)側の負担となります。
[参照URL: https://www.nakayamafudousan.co.jp/magazine/fudousan-rent/15282/]
しかし、入居者の使い方に原因がある場合は、費用を請求されることもあります。
例えば「トイレットペーパー以外の異物を流して詰まった」「子どもが誤っておもちゃを落とした」などは、入居者負担と判断される可能性が高いケースです。
[参照URL: https://corporation-lawyer.biz/fudousan/column/post462]
「えっ、そんなの知らなかった…」と思われるかもしれませんが、契約書や重要事項説明書に“故障時の費用負担ルール”が記載されていることが多いので、まずはその内容を確認してみましょう。
もしも記載があいまいだったり納得できない場合は、以下のような対応がおすすめです。
– 管理会社へ詳細を問い合わせ、トラブル内容や原因、費用の内訳を確認する
– 契約書のコピーを見ながら、費用負担の根拠を説明してもらう
– 消費生活センターなど第三者機関に相談してみる
費用請求が妥当かどうか、必ず納得のいく説明を受けてから判断するようにしましょう。
応急処置しても水漏れが続く…どうすれば?
まずは「止水栓」がきちんと閉まっているかを再確認してください。
止水栓は、トイレのタンク脇や床面にあるネジ状の部品で、時計回りに回すと給水が止まります。
[参照URL: https://www.esmile-24.com/toilet/column/detail/8294/]
ここが完全に閉まっていないと、応急処置をしても水が漏れ続けることがあります。
止水栓を閉めた上でも水漏れが止まらない場合、以下のような原因が考えられます。
– **タンク内部の破損**:ゴムフロートや排水弁が劣化・外れている
– **給水管の劣化**:配管の継ぎ目やパッキンが緩んでいる・割れている
– **便器そのものからの漏れ**:ひび割れや設置のズレなど
「どこから漏れているのか分からない…」というときは、タオルや新聞紙で便器周辺を囲ってみて、どの部分が濡れてくるかを観察すると発見しやすくなります。
それでも原因が特定できない場合や、水が広がるリスクがある場合は、無理をせず専門の業者に相談しましょう。
筆者の経験上、水漏れが悪化すると床材が傷んだり、階下への漏水につながることもあるため、早めの対処が肝心です。
トイレトラブルが続く場合、退去の理由になる?
基本的には、「設備不良によって生活に支障が出ている」ことを証明できれば、退去や契約解除の正当な理由になることもあります。
[参照URL: https://www.livable.co.jp/soudan/kojin-hojin/fudosan-058/]
ただし、以下のような前提条件が必要です。
– 修理依頼を何度も出しているが改善されない
– 管理会社や大家が明らかに対応を怠っている
– 故障が生活に重大な支障を与えている(例:使用不可な状態が長期間続いている)
これらに該当する場合、「契約不履行(貸主側の債務不履行)」として、退去や契約解除を検討できる可能性があります。
とはいえ、いきなり「もう出ます!」と自己判断するのではなく、以下のような段取りを踏むことが大切です。
– 管理会社へ文書で修理依頼を行い、その記録を残す
– 具体的な被害状況(使用できない日数、生活への影響など)を整理して伝える
– 専門家や法律相談窓口に一度相談してみる(自治体の無料相談なども活用可能)
「こんな状態で住み続けるなんて無理…」と感じたときこそ、冷静に証拠を整理し、段階的に交渉することが解決の近道です。
まとめ:賃貸トイレの故障は3ステップで冷静に解決
今回は、賃貸物件のトイレ故障に不安を感じている方に向けて、
– 契約書で確認すべきポイント
– 管理会社に伝えるべき内容
– 応急処置の正しいやり方
– 修理費の負担ルールと判断基準
– 緊急時の対応フローと注意点
上記について、水道修理の現場経験をもとに、安心して対処するための情報をお話してきました。
賃貸でのトイレトラブルは、「契約書の確認→管理会社への連絡→応急処置」という3ステップを踏むことで、冷静に対応できます。
費用の負担者や連絡先、緊急時の判断基準もこの流れで整理できるため、慌てることなく解決に向かえます。
たとえ夜間や休日でも、止水栓を閉めるなど基本的な対処を知っていれば、被害を最小限に抑えることができます。
まずは深呼吸して、契約書を確認し、管理会社への連絡から始めましょう。
そして不安なときは一人で抱え込まず、水回りの専門業者などにも遠慮なく相談してみてくださいね。